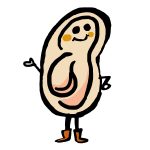頬がけいれんすることは、そんなに珍しくなく起こりますよね。
ただその原因や対処法となると、意外とご存じない方が多いのではないでしょうか。
今回は口腔外科医としての見地から、これらを詳しく解説してみたいと思います。
片側顔面痙攣

片側顔面痙攣とは、顔面の片側だけがピクピクとけいれんを起こす病気のことです。
片側顔面痙攣という名前は実は正式名称ではありません。正しくは片側顔面瘞攣といいます。
原因
片側顔面痙攣の原因は、動脈硬化です。
動脈硬化とは、血管の内側にコレステロールが沈着して、血管が弾力性を失い硬くなってしまうことです。
顔面部の筋肉の運動に、大きく関与する神経に顔面神経があります。
この顔面神経は脳神経のひとつで、第8脳神経という言い方もされます。
顔面神経は脳神経のひとつですから、脳から伸びてきて顔面部に広がる神経です。
顔面神経が脳から出てくるとき、脳の底のあたりを走行している血管と接触してしまうことが、片側顔面痙攣を発症させる原因と考えられています。
通常は接触しない血管が接触するようになった理由が、動脈硬化なのです。
症状
中高年の女性に比較的高頻度に認められます。
初期症状は、目の下あたりのけいれんです。
そして次第にけいれんを起こす範囲が拡大し、頬や口元、下顎、頚部へと広がっていきますが、額には起こりません。
あくまでも片側性なので、顔面部の左右両側がけいれんをおこすことはありません。
ひどくなると目を開けることも難しくなります。
顔面神経は運動神経です。
感覚を支配する神経ではないため、片側顔面痙攣を起こしても顔面部の感覚がしびれたり、なくなってしまうことはありません。
診療科
片側顔面痙攣は顔面神経に起こる病気ですので、神経に関わる病気の診療科である脳神経外科や神経内科を受診することをお勧めします。
治療法
ここでは3つの治療法を紹介していきましょう。
薬物治療
片側顔面痙攣の薬物治療では抗けいれん剤が使われます。
ストレスによってけいれんが起こってくることもあるので、精神安定剤が投与されることもあります。
しかし、どちらも著しい効果に乏しいです。
ボツリヌス療法
片側顔面麻痺の治療にボツリヌス療法が行なわれることもあります。
筋肉を動かす時には、運動神経からの指令をアセチルコリンという神経伝達物質が伝えているのですが、ボツリヌス療法ではボツリヌス菌の毒素を注射して、注射した部位のアセチルコリンの働きを抑えます。
つまりボツリヌス療法は、神経の筋肉への伝わりを遮断することで、けいれんが起きないようにする治療法です。
ボツリヌス療法の効果は、永続的にもたらされるものではありません。
個人差がありますが、3〜4ヶ月程度しか持続しません。
したがって、数ヶ月ごとに注射を受ける必要があります。
美容目的でもボツリヌス療法は行なわれますが、片側顔面痙攣の治療法のボツリヌス療法では美容目的の治療とは異なり、健康保険を使って治療を受けることが出来ます。
外科手術
薬物治療やボツリヌス療法では、けいれんが改善しない様な難症例の場合は、頭蓋内神経血管減圧手術という外科手術が行なわれます。
頭蓋内神経血管減圧手術は、顔面神経に接触している血管が顔面神経と接触しないようにすることが目的です。
まず、耳の後方に切開を加え、頭蓋骨に穴をあけて手術用の顕微鏡視下で、顔面神経を圧迫している血管の位置を動かしたり、血管と顔面神経の間にスペースを作るために人工材料を入れたりします。
この治療法での片側顔面痙攣の治癒率は80〜90%ととても高いとされています。
その反面、合併症のリスクもあり、顔面神経が麻痺して顔の筋肉が動かしにくくなったり、聴力が低下して耳が聞こえにくくなったり、脳を傷つけることで死亡したりする可能性も否定できません。
顎顔面部のジストニア

ジストニアとは、無意識に身体を動かしてしまう病気のことです。
ジスキネジアは、お口やその周辺だけに生じるものではありません。首やまぶたなど他の部位にも発症します。
お口を開け閉めする筋肉である、咀嚼筋に起こった場合を特に口顎ジストニアということもあります。
口顎ジストニアの症状は、顎関節症と似ていますので注意が必要です。
原因
ジストニアは、原因がよく分かっていない特発性ジストニアと、そうではない症候性ジストニアにわけられます。
特発性ジストニアの原因は今だ不明ですが、大脳の基底核のあたりや中枢神経系に、何らかの障害がおこっているのではないかと考えられています。
症候性ジストニアについては、向精神薬やパーキンソン病の治療薬などの副作用でおこる薬剤に原因があるものや、脳に生じた腫瘍性病変などの神経疾患により起こるものがあります。
症状
ジストニアは無意識に身体の一部を動かしてしまう病気ですが、動かすことを制御することは出来ません。
自分自身で止めようとしても止められない動き、すなわち不随意運動であることがジストニアの特徴なのです。
症状が軽ければ、意識すれば筋肉の動きを自分自身でコントロールできる場合もありますが、極めて稀です。
自分の意思でコントロール出来ないだけでなく、重症化すれば食事や会話等の日常生活にも支障を来すようになります。
なおジストニアの特徴として、寝ている間にはほとんど現れません。
顎顔面部に生じたジストニアは、舌を前方や横方向に動かしたり、下顎を前や横に動かしたりします。
また症状として、
- お口を常に開けてしまうもの
- 無意識にぎゅっと閉じてしまうもの
- 開けたり閉めたりを繰り返すもの
このように様々です。
これらのすべてが起こることもあれば、限られた症状のみ発現することもあり、病態は一定ではありません。
お口の開閉口にジストニアは起こらず、舌にのみジストニアが起こった場合、頬を内側から舌が押し出す動きを起こすので、頬が常に張ったり引っ込んだりを繰り返してしまいます。
ジストニアを生じる筋肉は、片側性であることもあれば、両側性に起こることもあります。
診療科
顎口ジストニアに関しては脳神経外科や神経内科などの、神経疾患を専門に診察する科を受診することをお勧めします。
治療法
ジストニアの治療法については、特発性ジストニアか症候性ジストニアかによって異なりますが、薬物治療が治療の第一選択である点は共通しています。
特発性ジストニアの場合は、副交感神経遮断薬や筋弛緩薬、抗不安薬を処方します。
症候性ジストニアの治療の場合、原因となった薬剤の投与開始後間もなく発現した症例では、副交感神経遮断薬の注射がよく効きます。
しかし、長期間の薬剤使用後に生じた症候性ジストニアの場合は、副交感神経遮断薬の効果はあまり期待できません。
原因と考えられる薬剤の投与を中断すれば、ジストニア症状が改善する可能性があるので、主治医に休薬を依頼します。
チック

チックとは、顔面、頚部、舌、手足など身体の一部に、突発的な速い収縮を瞬間的に生じ、それを不規則な間隔で繰り返す病気のことです。
原因
精神的なストレスや疲れといわれています。
症状
顔面に生じるチックでは、顔の表情を形作る筋肉である表情筋に症状が現れます。
頬筋に症状が現れた場合は、頬がピクピク動いたり、けいれんしたりします。
頬以外にも、まぶたや鼻、口などいろいろなところにおこります。
チックのけいれんの特徴は、自分自身でコントロールすることが出来る点にあります。
診療科
顔面のチックが疑われる場合は、神経内科や心療内科の受診をおすすめします。
治療法
ストレスをためないことが大切なので、日常生活の指導が行なわれます。
薬物治療では、ハロペリドールという抗精神病薬が有効とされています。
まとめ
頬にけいれんを引き起こす病気はいろいろあります。
自分自身でコントロールできるけいれんと、そうでないけいれんとがあります。
けいれんが不安なときは、まず神経内科などの神経疾患を扱う専門診療科を受診することをお勧めします。